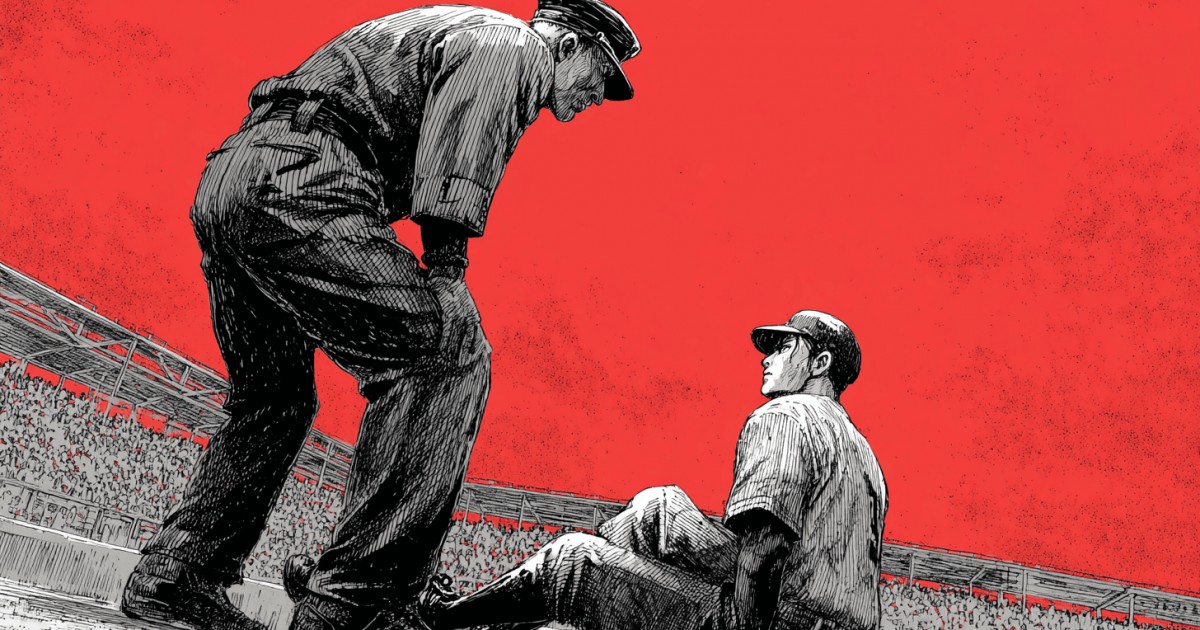■増産バンザイじゃね!?
2日前に開催された「関係閣僚会議」で、農林水産省は長年にわたる生産調整政策の誤りを、ようやく公式に認めた。
これを受けて石破総理と小泉農水大臣が記者会見を行い、「コメの増産」に方針を転換する姿勢を明らかにした。
この決断は、酷暑とコメ不足という「危機」のお陰で、これまで溜まりに溜まっていた農水省の失策の膿がようやく出はじめたことを意味している。
ボクは、この現象じたいが「天の恵み」なんだと思う。
これまで「天に唾」してきた報いの結果だ。
長らく「ステルス減反政策」を続けてきた農政は、ここでようやく増産にかじを切った。
お米の専業農家にとっては「増産バンザイ」のハズ。
しかし、オールドメディアでは「今さら増産などできるわけがない」と嘆く農家の声ばかりが取り上げられている。
確かに、放棄された水田を再生させるには大きな労力が伴うだろう。失策続きの農水省を怒る気持ちも理解できる。
だが、増産=販売増のチャンスが到来しているにもかかわらず、それを歓迎しない農家の姿勢には疑問を抱かざるを得ない。
以前の記事でも触れたが、オールドメディアが映像に出演させる「高温障害で不作」になったと主張する野菜&果樹農家の多くは、経営・知識・技術のいずれにおいても二流・三流の域を出ていないのが現実。
批判を恐れずにいえば、稲作農家も同様だ。
「お米増産政策」を歓迎しない農家の多くは、経営・技術・知識のいずれにおいても一流とは言い難い方だと推測する。
だが、問題の本質は農家の個別能力だけではなく、農水省の政策思想の古さ、そして現場への一貫したミスリード体質にある。
▼一流農家は常に未来を見据えている
現実的に、今年の酷暑でも、同じ環境下でも的確な準備によって健全な生産を継続している農家は各地に存在している。
彼らは、昨年の秋の収穫後には次のような対策を講じ、変動する気候に対応している。
▸ 秋起こしや緑肥による地力の維持
▸ 冬水管理による生態系保全
▸ 乾田直播による省力化と水管理の柔軟化
▸ 高温耐性品種(ゆうだい21など)の導入
▸ 点滴灌水などによる干ばつ対策
▸JA主導による基肥主体の施肥設計ではなく
▸気象変動に対応可能な追肥主体の施肥設計
これらは単なる技術の問題ではなく、経営判断と情報感度の質が問われている。
▼農水省が繰り返してきた構造的なミスリード
農水省は、過去十数年にわたり毎年10万トン単位でコメの供給抑制政策を続けてきた。
「米は余る、需要は減る」という固定観念に基づく政策判断が、その背景にある。
しかし、コロナ禍以降、内食需要の増加、輸出需要の拡大、さらには代替穀物としての米への再評価など、需要は単純な減少傾向にはない。
にもかかわらず、農水省はその需要見通しの誤りを認めず、「調整在庫の不足」や「流通の目詰まり」などの説明で誤魔化してきた。
この姿勢は、行政機関としての信頼性を著しく損なう。
▼食管法の亡霊に囚われたままの農政
農水省の最大の問題は、食糧管理法(食管法)廃止から四半世紀が経過した今なお、旧来型の上意下達の農政思想を引きずっていることにある。
市場環境は変動し、民間は気象・価格・需給の変化に柔軟に対応しているにもかかわらず、政府は一本の見通しに固執し続けている。
これはもはやリスク管理の放棄に等しい。
ある経済学者も指摘しているように、民間は多様なシナリオを提示することでリスクを分散し、当たり外れが共存できる。
一方、政府の一本見通しは、その失敗が即、政策全体の崩壊を招く。
▼農水省は稲作専業農家の足を引っぱるな
小泉農水大臣が「生産調整の終焉」を明言したことは前進だが、補助金の削減だけが先行すれば、耕作放棄地の拡大は避けられない。
求められているのは、次のような構造改革である。
▸ 土地利用の集約化・大規模化の推進
▸ 面積に応じたインセンティブの導入
▸ 農地譲渡の促進
▸ 精密農業技術への設備投資支援
政府はもはや、農家を指導・統制する主体ではなく、民間の創意工夫を支える「インフラ」として機能すべきである。
▼本当に守るべきは何なのか!?
「異常気象で不作だった」と語る背景には、農家自身の経営能力の問題がある。
しかし、より大きな構造的要因として、政府の情報操作や政策判断の誤りがあったことは否定できない。
常に、時代の変化を先読みし、情報を読み解き、リスクを取って投資し、成果を得ようとする農家がいる。
依存型農家を優遇する政策は、結果的に全体を沈めてしまう。
この問題は単なる気象変動の話ではない。日本の農業を支える仕組みそのものが、時代に取り残されているのだ。
その仕組みを変えられるかどうか。
それが、私たちの「食」の未来を左右するのである。
すでに登録済みの方は こちら