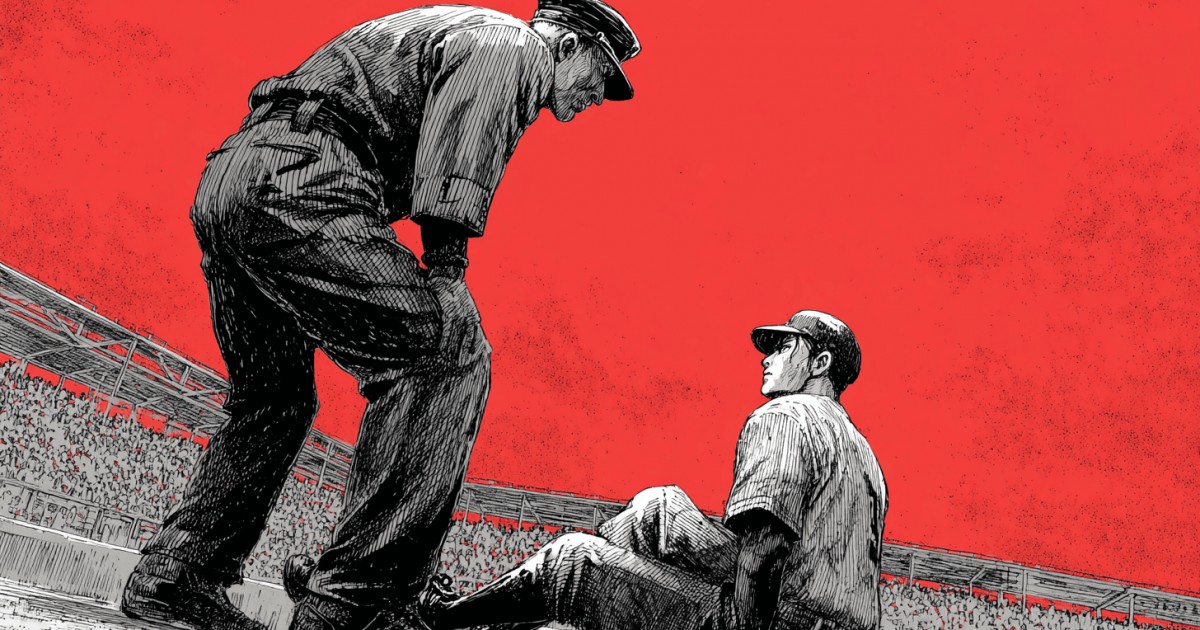■本のタイトルはガッカリだけど、本の中身は温暖化対策に迷走中の人類必読の書
この書籍の原題は『Der lange Atem der Bäume』(ドイツ語)です。
日本語に直訳すると、木々の長い呼吸 / 樹木の長いため息 / 樹木の長い息吹」といった感じです。
日本語訳のタイトルは、ダサすぎてガッカリだけど、
本の中身は森の監視官という現場仕事に裏付けされた視点による慧眼に溢れていました。
▼森は地球のエアコンである
地球温暖化が深刻さを増す中で、私たちは再生可能エネルギーやカーボンニュートラルといった人間が中心の解決策に注目しがちです。
しかし、著者のペーター氏は『樹木が地球を守っている』は、「森」の存在こそが、人間の最先端科学による解決策をはるかに凌ぐ最も優れた気候コントローラーであるという根本的な視点を私たちに突きつけます。
▼森は気候を創っている
本書の中で強調されているのは、森林の機能は単にCO₂を吸収するだけでなく、雨を降らせ、風を生み、気温を下げる存在であるという点です。
たとえば、広大な森が発生させる水蒸気は、数千キロ離れた地域に雨をもたらします。
これは、森は「被害を受ける側」ではなく、「地球の気候を担う主人公」であるということに他なりません。
▼気候変動への“適応力”をもつ樹木たち
気温上昇や干ばつに直面した木々は、受動的に朽ちていくのではなく、自ら学習し、対応する戦略を変えている、というのが著者ペーター氏独自の新たな見解です。
具体的には、光合成を一時停止したり、葉を早期に落とすことで水分蒸散を抑えるなど、まさに自己調整型の生命体です。
▼森林破壊は「気候調整装置」の破壊
本書では、林業の経済合理性がもたらす「伐採」こそが、森の気候調整機能を破壊し逆に干ばつや猛暑を招く、という警告を発しています。
これは、自然を「資源」としてしか見ていない、人間たちの視点への痛烈な批判です。
▼希望は「人間は何もしないこと」にある
著者が提示する最も有効な気候対策は、皮肉ながら「人間が森に手を出さないこと」だと主張しています。
森は自力で再生する能力を持ち、それには人間の“手助け”ではなく、再生するための「時間」と「静寂」が必要だからです。
これは、従来の人間による森林開発型のアプローチに対する根本的なアンチテーゼです。
▼人間の最先端科学技術でも代替できない「森の力」
著者ペーター氏は次のように断言します。
「いかにAIや再エネが進化しても、森が果たしている地球規模の調整能力には及ばない」
「樹木の能力は、人類のいかなる最先端科学技術よりも優れている」
人間は自然をコントロールするよりも「自然の力に委ねる覚悟」を持つべき時期であることに気がつくべきなのです。
▼森は「人間の協力を必要としていない存在」である
『樹木が地球を守っている』が私たちに伝える最大のメッセージは、「森林は人間が壊してはならない存在であり、森林の回復機能を信じて見護るべき」だということです。
温暖化という人類最大の課題において、最も費用対効果が高く、同時に最短の解決策は、人間は森の木をこれ以上は伐採せず、森の回復を森に任せることが一番大事な選択だということのようです。
すでに登録済みの方は こちら