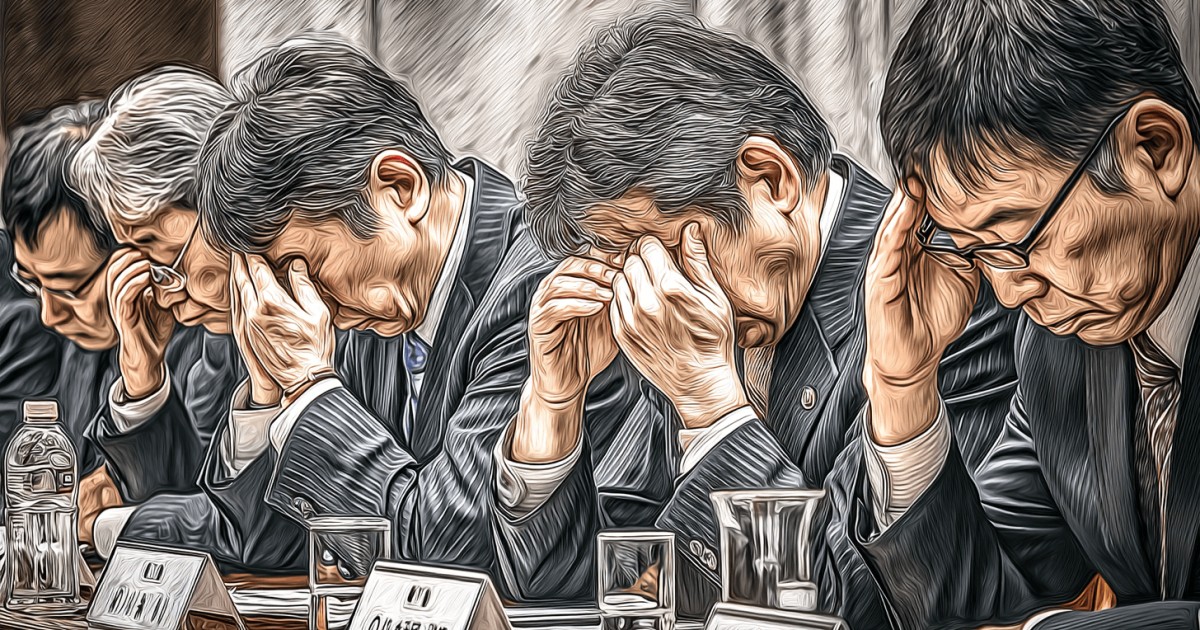■灼熱と旱魃の黙示録
太陽(火)に焼かれ、渇く日本列島の現状を『聖書』から読み解く
新米の収穫が危ぶまれ、コメ農家からは「過去最悪かもしれない」と悲鳴が上がる。
ダムの貯水量は平年の半分以下に落ち込み、各地でプールの営業中止が相次いでいる。
そして、関東では今年初となる気温40度超を記録。
4日連続での40度超えは、観測史上最長レベル。
もはや「異常気象」では済まされない、構造的異変が進行している。
今日日はキリスト教の安息日=日曜日。
ボク自身はキリスト教徒ではないが、キリスト教徒約25億人、イスラム教徒20億人、ユダヤ教徒を含めれば、『聖書』という書物が人類文明に与えてきた影響力は、決して無視できない。
そして、その『聖書』の中に......
今まさに私たちが直面している「灼熱」と「渇き」の風景と不気味に重なる記述が、『聖書』には確かに存在している。
▼焼き尽くす太陽──終末の“熱”と人類の硬化
「第4の御使いが鉢を太陽に注いだ。
すると太陽は人々を火で焼くことを許された。
人々は激しい熱に焼かれ、それでも彼らは、その災いを支配する神の名を冒涜し、悔い改めて栄光を帰そうとはしなかった。」
➔ヨハネの黙示録16章8〜9節
この一節は、単なる終末の幻ではない。
「人類が悔い改めることを拒んだ結果としての灼熱」という構造を、明確に描いている。
科学はCO₂を主因とするが、聖書は霊的な頑なさこそが、熱と乾きの根本要因だと告げている。
▼干ばつは「物理現象」か、それとも「霊的徴(しるし)」か
「わたしが雨を止め三か月も雨を降らせず、ある町には降らせ、他の町には降らせず、一つの畑には雨が降っても、他の畑には降らず、枯れてしまった。」
➔アモス書4章7節
日本列島では、今、ダムが干上がり始めている。
水田のひび割れ、用水路の涸渇、プールの営業停止。
水の消失は、実体的でありながらも象徴的な出来事だ。
「主が空を閉ざし、雨が降らず、地に作物が実らなくなるのは、あなたたちが罪を犯したからである。」
➔列王記上8章35節
これは「神の怒り」ではなく、「神との断絶によって、祝福が絶たれた状態」の描写である。
水が枯れるとは、天とのパイプが閉ざされたということなのかもしれない。
▼悔い改めと回復の構造──人が変われば地も癒える
「この民がへりくだり、祈り、わたしの顔を求めて悔い改めるなら、わたしは天から聞いて、彼らの罪を赦し、彼らの地を癒す。」
➔歴代誌下7章14節
この一節は、環境の回復は霊性の回復に伴って起こるという原理を示している。
技術や対策では解決しきれない領域に、神学的な視座があるのではないか。
「地球環境の問題は、文明全体の魂の問題である」
『聖書』はそう警告しているようにも聞こえる。
▼日本列島のコメとプールの叫びが、天に届いていないとしたら
・新米の危機は、ただの農業問題なのか?
・水源の枯渇は、ダムの問題なのか?
・人の心が渇いたとき、大地もまた応えるのではないか?
「被造物は、共にうめき、共に産みの苦しみをしている」
➔ローマ人への手紙8章22節
気候変動の裏にある「産みの苦しみ」とは、新たな文明への移行か、あるいは滅びの序章か。
▼いま、この記述をどう読み解くか
「聖書を学ぼう」
「信仰を持とう」
そういうことを言いたいのではない。
だけど、2000年以上前に書かれたこの文言が、まるで今の日本列島を描いたかのように感じられるのは、なぜだろうか?
太陽が人々を焼き、雨が止み、地がひび割れ、作物が枯れる。
この記述を、いま私たちはどう解釈すればよいのだろうか?
答えはまだ出ていない。
だが、見て見ぬふりをしてよい段階は、もう過ぎているのかもしれない。
すでに登録済みの方は こちら